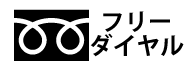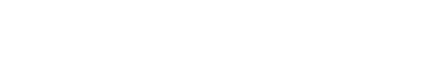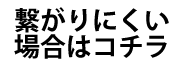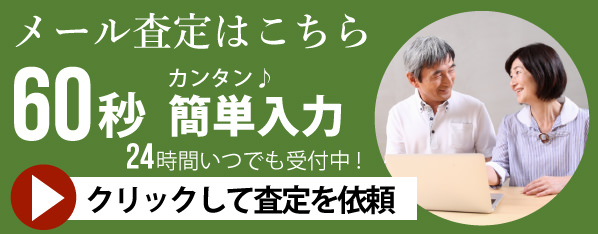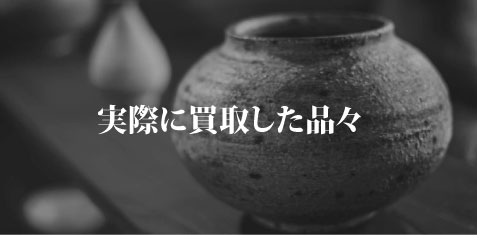陶器・焼き物
の買い取りは
経験豊かな鑑定士と
実績多数の一灯舎へ
陶器・焼き物の買取は、
一灯舎にお任せください。
最高額の価値を見出し、買い取り致します。
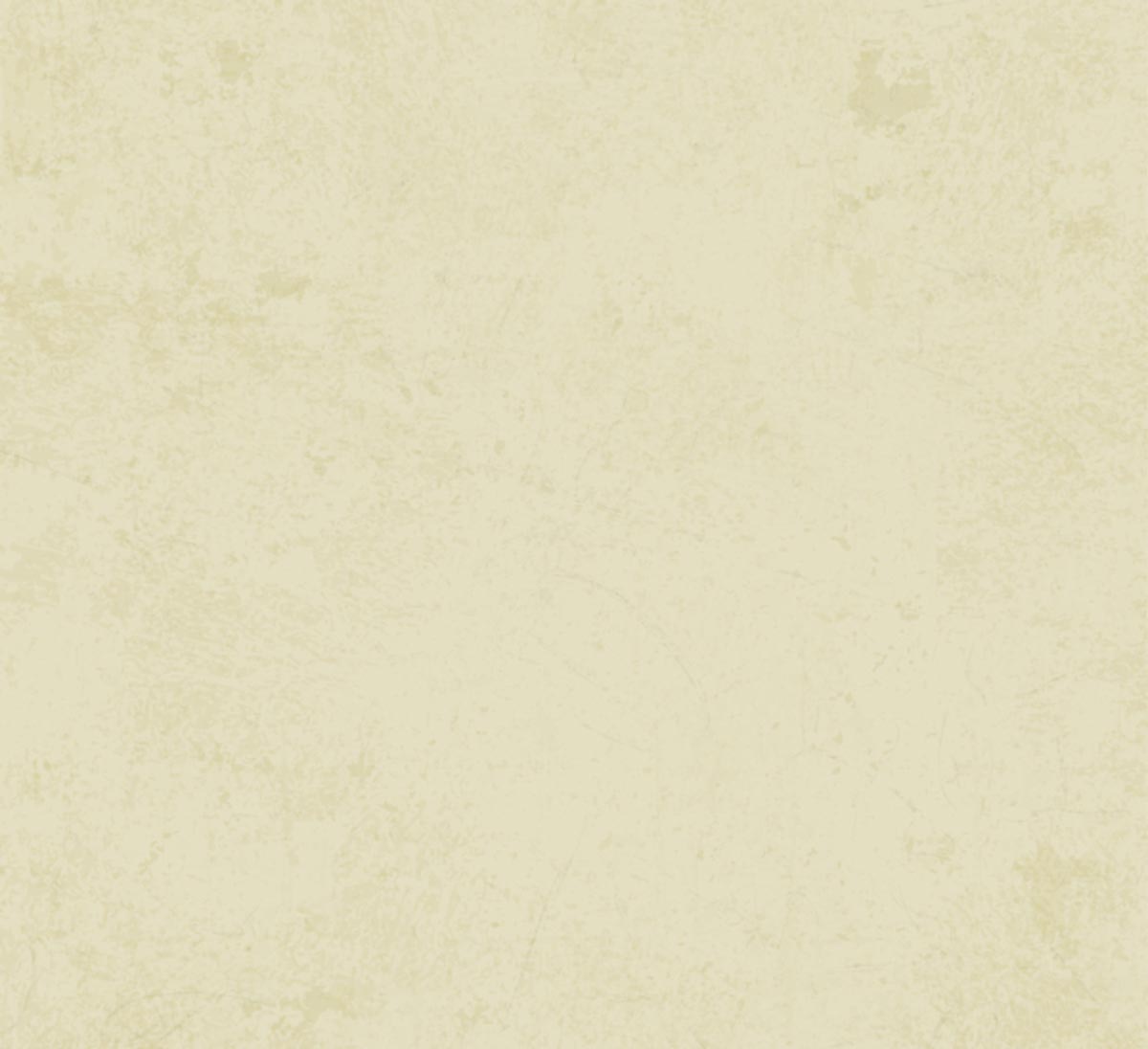
一灯舎が選ばれる理由
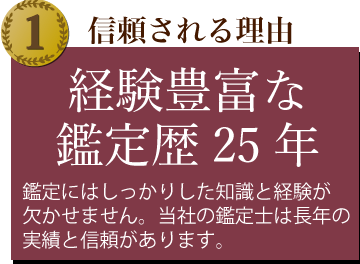
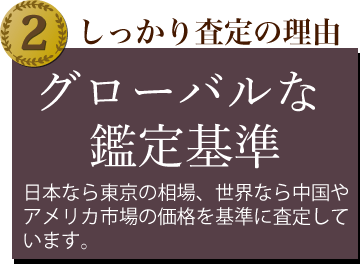
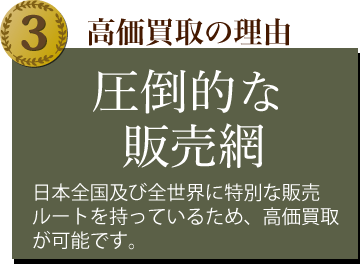

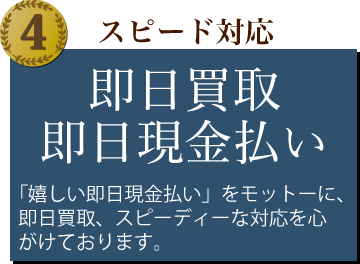
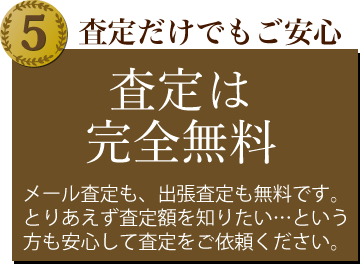
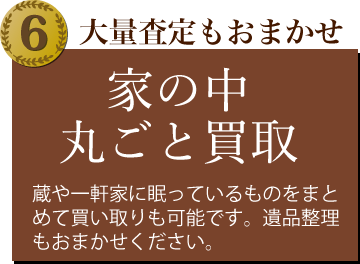
陶器・焼き物
陶器、焼き物の歴史は非常に古く、 日本のやきもの歴史について解説します。
日本では約1万2000年前の世界最古の土器が発見され、日本の焼き物は世界で最も古く長い歴史をもっています。その後の日本における焼き物の歴史は、中国や朝鮮の影響を受け育ってきました。その後朝鮮からろくろ技術と、窯が伝わり、轆轤によってさまざまな形やデザインのものが作られるようになり、窯が伝わったことで1000度以上の高温焼成が可能になりました。須恵器に見られるように、水漏れせず壊れにくい陶器の焼き物が焼けるようになったのです。
そして焼き物は全国各地で今もその生産が行われており、代表的なものは下記があります。
・有田焼…有田焼は1616年の李参平による泉山陶石の発見に始まり、1597~1598年の慶長の役で、鍋島軍が朝鮮からの引き上げの時に、日本に持ち帰った陶工です。
・萩焼…山口県萩市で今も焼かれている陶器です。一部長門市などにも窯元があり、長門市で焼かれる萩焼は、深川萩(ふかわはぎ)と呼ばれています。古くから茶人好みの器を焼いてきたことで知られており、お茶道具などで度々登場します。今でも多数の窯元が存在し、日本中でも有名な窯元となりました。
・伊万里焼…日本で磁器が焼かれるようになったのは、約400年前の豊臣秀吉の朝鮮出兵後の有田(現在の佐賀県有田町)が最初だといわれています。きれいな絵付けのある絵皿などが代表的で、実用と美術品としての両方が楽しめます。
・唐津焼…唐津は古くから九州の対外交易場所であったため、安土桃山時代から早くも陶器の技術が伝えられていたと言われており、今も佐賀県の岸岳諸窯など各所に窯場跡があります。
・備前焼…六古窯の一つの備前焼は、伝統的な歴史があり、平安時代に作られた須恵器の流れをくんで、おもに壺(つぼ)・甕(かめ)・擂り鉢(すりばち)などの庶民の日常品として使われるものが多く焼かれてきました。独特の茶色の深みとザラ味が特徴の焼き物です。現在でも多くの方々に愛されています。
・美濃焼…美濃焼の歴史はとても古く、平安時代には灰釉陶器が焼かれ、一般民衆のための無釉の山茶碗なども焼かれていました。今でも多くの品を生産し続けています。
・常滑焼…平安時代末期には、常滑を中心にして知多半島の丘陵地のほぼ全域に窯が築かれ、山茶碗や山皿、壷などがたくさん作られました。今でもその跡地が多く見受けられます。

陶器・焼き物の買い取りは、鑑定歴25年以上、実績多数の一灯舎におまかせください。

古伊万里から現代作家、人間国宝の焼き物、陶器まで幅広く買い取り致します。
一灯舎では毎日焼き物の買い取りがある為、八王子でも随一の目利きで買い取りが可能でございます。
上記のような萩焼や備前焼、伊万里焼、美濃焼、常滑焼、唐津焼、有田焼のみに限らず、瀬戸焼、江波皿、現代作家もの、お茶道具としての焼き物、絵皿、蔵から出てきた名もわからない古い皿まで幅広く買い取り出来ます。焼き物や陶器、陶磁器、青磁など日本国内のみならず朝鮮や中国などシナ半島のものまで査定.買い取り可能でございます。
特に共箱、桐箱に入っていたり作家が分かるものは断然高く買い取り、最大の金額をご提示できます。焼き物の買い取りは一灯舎にお任せ下さい。
買い取り強化作家
- 酒井田柿右衛門
- 金重陶陽
- 井上萬二
- 永楽善五郎
- 伊勢崎淳
- 加守田章二
- 加藤卓男
- 藤原雄
- 今泉今右衛門
- 宮川香雲
- 諏訪蘇山
- 徳田八十吉
- 永楽 善五郎